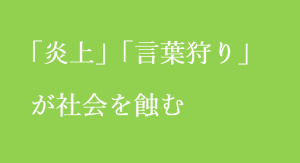『ながい坂』山本周五郎 <第19回>
山本周五郎『ながい坂』上・下、新潮社、2021年(初版1966年)
この本は、昭和39年(1964)6月29日号から、昭和41年(1966)1月8日号まで1年半のにわたって雑誌「週刊新潮」に連載され、完結直後の2月と3月に新潮社から上下2巻として刊行されている。作者の山本周五郎は、その翌年、昭和42年に63歳で死去している。完結した作品としては、本作品が生前最後の長編小説となった。
読売新聞特別編集委員の橋本五郎さんがテレビでこの本を紹介されていたのを見たのが、この本を読むきっかけとなった。橋本さんが紹介された一節に僕も共感を覚えたからである。
その一節は、以下のような言葉であった。
「(中略)人の一生はながいものだ、一足飛びに山の頂点へあがるのも、一歩、一歩としっかり登ってゆくのも、結局は同じことになるんだ、一足飛びにあがるより、一歩ずつ登るほうが途中の草木や泉や、いろいろな風物を見ることができるし、それよりも一歩を慥(たし)かめてきた、という自信をつかむことのほうが強い力になるものだ、わかるかな」(小出方正(藩校・藤明塾の教師)が阿部小三郎(三浦主水正)に言った言葉(上巻33・34頁))
初めてこの文章を読んだとき、自分の人生とも重ね合わせて感じさせられた。また僕自身が体験した富士山登山ともぴったりとその想いが重なり合ったのである。
山本周五郎が『ながい坂』という表題に込めた想いについて、近代日本文芸研究者の奥野政元さんは解説の中で次のように述べている。
「意識の自由を保持し続ける忍耐が、勇気に支えられた練達を生み出し、やがて展望の開かれた希望を生み出す、その時の展望そのものが、ながい坂でもあったのであろう。」
奥野さんは、『ながい坂』には、山本周五郎の死の予感と決意が込められていると言っている。(奥野政元「解説 作者自身の死の予感と決意」)
山本周五郎がよく引用するブラウニングの言葉
「人間の真価はその人が死んだとき、何を為したかではなく、彼が生きていたとき、何を為そうとしたかで決まるのである。」
この小説の中でも僕がアンダーラインを引いた一節がある。
「(中略)人間は生まれてきてなにごとかをし、そして死んでゆく、だがその人間のしたこと、しようと心がけたことは残る、いま目に見えることだけで善悪の判断をしてはい けない(中略)」
「(中略)いちばん大切なのは、そのときばったりとみえることのなかで、人間がどれほど心をうちこみ、本気でなにかをしようとしたかしないか、ということじゃあないか、そうは思えないか」(三浦主水正が関蔵(新畠を開墾する農民)にいった言葉(下巻209頁))
僕が山本周五郎の本を読んだのは、この本が初めてである。この本は、ちょうど僕が生まれる1年前に刊行された本であり、山本周五郎の最後の長編小説であることもこの本を読んで知った。刊行されてからすでに50年余し経っていることになる。今回、最晩年の山本周五郎作品に触れることができて、とても幸せだった。